速水御舟の革新的な「炎舞」
夜の静けさの中、ふと目を閉じる。まぶたの裏に映るのは、
燃え上がる炎のゆらめき。その周りを、ひらひらと舞う蛾たちの儚い姿——。
速水御舟の『炎舞』は、一度目にしたら忘れられない不思議な魅力を持つ作品です。
この絵に惹かれるのは、そこに「生」と「死」が同時に存在しているからかもしれません。
燃え尽きる炎、運命に導かれるように舞い続ける蛾。
それは、私たちが生きるということそのものを映しているようにも思えます。
速水御舟と『炎舞』——感性が研ぎ澄まされる世界
速水御舟(1894-1935)は、日本画の世界に革新をもたらした画家。
彼の作品には、静謐な美しさと大胆な感性が共存しています。
1925年(大正14年)に描かれた『炎舞』は、そんな御舟の感性が極限まで研ぎ澄まされた一枚。
燃え盛る炎の光と影が織りなす舞台の中で、蛾たちが命の輝きを放ちながら飛び交います。
この絵に込められたのは、決して燃え尽きることのない「情熱」、
そして、それが消える瞬間まで美しくありたいという「願い」なのかもしれません。
写実の追及、そして写実を超えて
写実を追求して、「京の舞妓」という作品を描き上げます。
真実をつかむため、敢えてあさましく描こうと徹底した細密画は、酷しく批判されました。
大家、横山大観は激怒し、悪写実と酷しく批判したのです。
御舟自身、次第に写実一辺倒になっていくことに悩みました。
そこから、真実をつかみださなけれぼならないと悩みました。
写実を突き詰めた先でつかんだものが、「炎舞」という作品だったのです。
炎は螺旋を描いて舞い上がり、まるで生命のほとばしりのようです。
伝統的な日本画は輪郭線を描くことを基本としています。
日本画としては、新しい、輪郭線を描かない朦朧体という技法に横山大観は挑みますが、
日本画ではないという批判を受けやめています。
御舟の炎舞は、まさに試行錯誤の結果、この朦朧体を完成させた作品になっています。
新しい表現を求め、西洋の絵のように、空気を捉えようと、伝統を打ち破り完成させた名作なのです。
『炎舞』に漂う幻想の世界——朦朧体の技法
『炎舞』が持つ独特の美しさは、日本画の伝統技法「朦朧体」によるものです。
🔹 朦朧体とは?
輪郭を明確にせず、ぼかしやにじみを活かした幻想的な表現。
速水御舟は、この技法を駆使して炎の光と影を描き出しました。
『炎舞』の炎は、まるで画面の中でゆらめいているかのよう。
闇に溶け込むように舞う蛾たちは、光を求めながらも、その光に翻弄される存在として描かれています。
この技法が生み出すのは、現実と幻想の狭間。私たちの心にすっと入り込み、どこか懐かしく、それでいて切ない感覚を呼び起こします。
『炎舞』に託されたもの——生の美しさと儚さ
この作品を見つめていると、胸の奥が少しざわめくような感覚に襲われます。
それは、ここに描かれているものが、私たち自身の生きる姿そのものだからかもしれません。
炎は何を象徴するのか?
情熱と輝き——どんなに激しく燃えても、やがて消えてしまう。
終わりのない求道——私たちもまた、何かに向かって燃え続けている。
蛾の羽ばたきに込められた意味
惹かれるものに飛び込まずにはいられない本能
美しく散ることの切なさ
御舟は、この作品で「人が生きるということ」を静かに語っています。
それは、限りある時間の中で、自分の光をどう燃やすかという問いなのかもしれません。

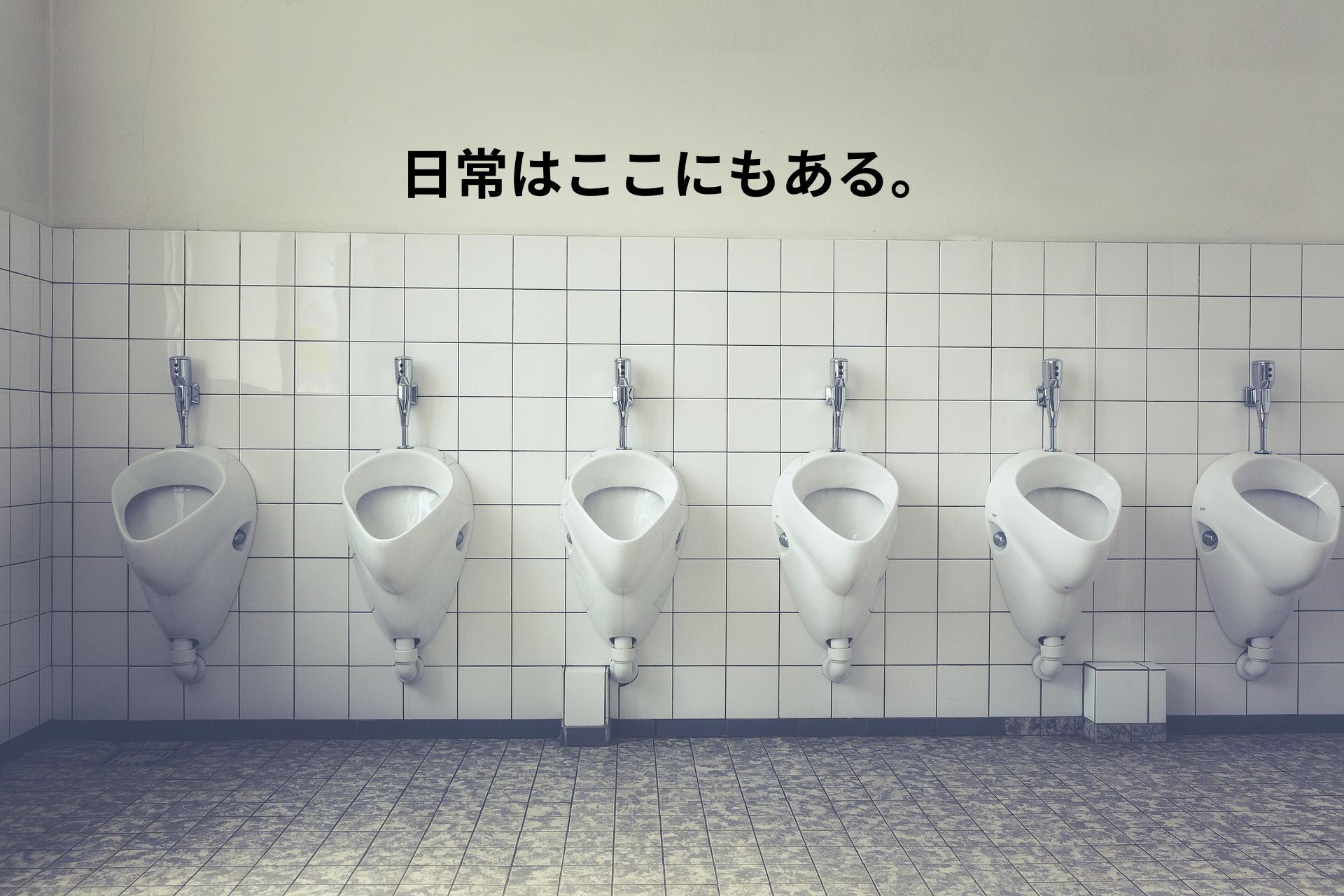


コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。