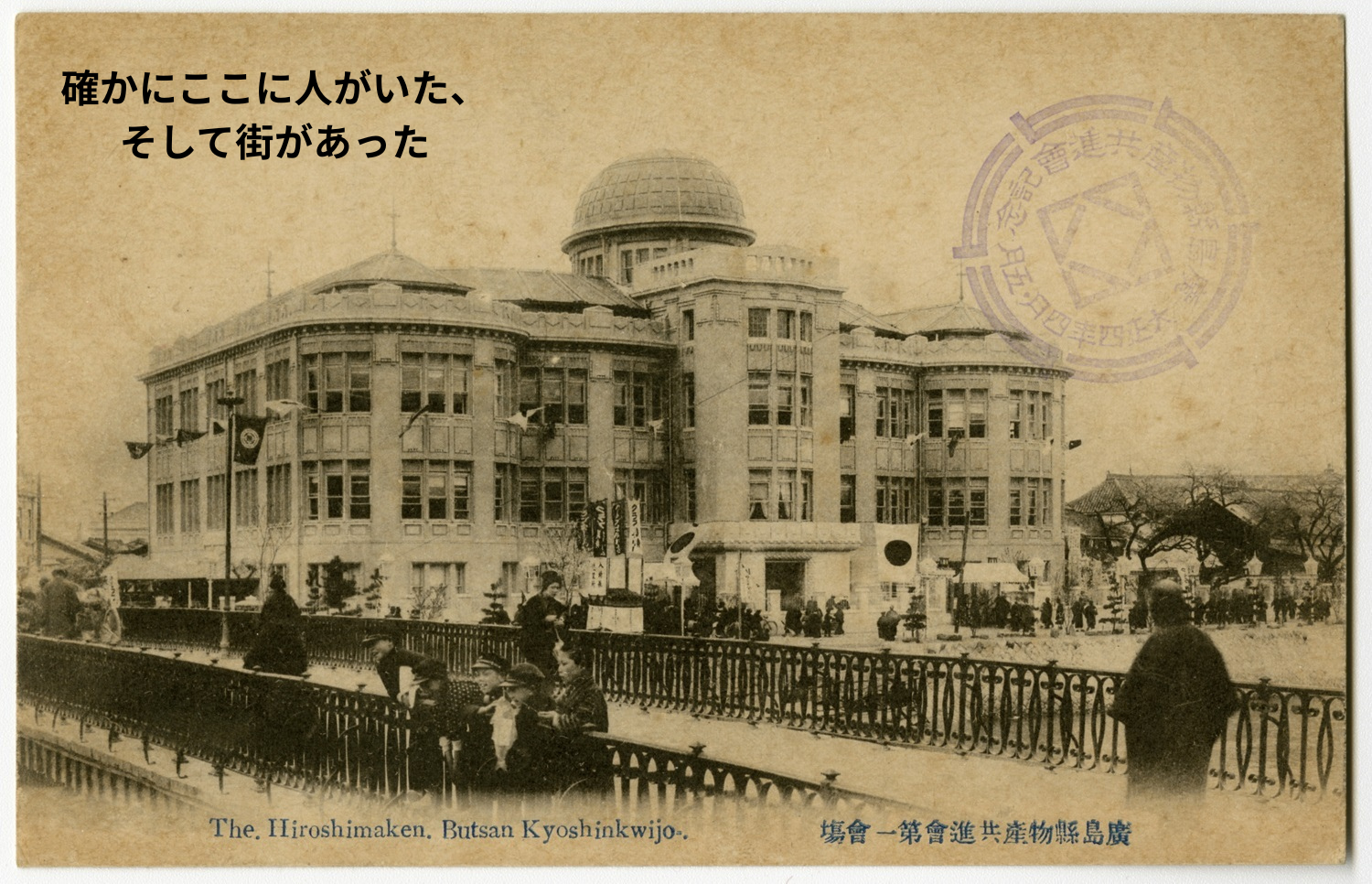田沼意知が刺された日
天明四年(1784年)四月、江戸城内で一人の若き老中が刺された。
田沼意知──父はかの田沼意次。
享保の改革以降、貨幣経済と流通を推進した近世的な政治家だが、その子・意知自身は清廉で有能な若手官僚とされていた。
だが、その実像は事件によってかき消される。
刺したのは佐野政言という旗本。
事件の詳細は曖昧なままだが、当時の田沼家に対する民意の鬱屈が彼に託されたのは間違いない。
そして事実を他所に、佐野政言は死後“佐野大明神”として民間で神格化される。
腐敗の象徴を斬った英雄という語りが、瞬く間に広がったのだ。
では、本当に正義を遂げたのか?
田沼意知は、なぜ殺されなければならなかったのか?
その問いからすべてが始まる。
正義を欲したのは、誰だったのか?
佐野政言の刃は、民意によって「正義」とされた。
だが、それは彼自身の信念というより、「そうであってほしい」という民衆の欲望が作った正義だった。
ここで思い出すのは赤穂事件だ。
浅野内匠頭が吉良上野介に刃傷に及び、切腹。その後、赤穂浪士が吉良邸に討ち入る。
内匠頭の刃は未遂に終わったが故に仇討がなされ、浪士たちは忠義の美談として語り継がれた。
一方、吉良は冷酷非道な悪役として歴史に残った。
だが史実を見ると、吉良は教養ある穏やかな人物であった可能性が高い。
つまり民衆が求めたのは、筋が通った話ではなく、自分が納得できる物語だったのだ。
そしてその構造は、佐野政言の“神格化”にも重なる。
人は見たいものしか見ない──心理の構造
ここで視点を変えたい。
問題は事件そのものではない。
人間の「目」にある。
心理学には「認知バイアス」という概念がある。
人は見たい情報だけを選び、信じたい物語だけを拾う性質がある。
たとえば、
確証バイアス:自分の意見に合致する情報ばかり集める
同調バイアス:周囲の雰囲気に逆らえない
ストーリーバイアス:事実よりも整った“物語”に納得してしまう
田沼が腐敗の象徴とされたのも、佐野政言が神とされたのも、そして吉良が悪役とされたのも、すべて私たちの“目のクセ”の結果なのかもしれない。
私たちは真実を見ているつもりでも、実は自分の欲望を見ているだけなのだ。
スポンサーリンク
語られることで変質する「正義」
正義は、正しいことをした人が得るものではない。
正義とは、物語として「語られる」ことで与えられる称号である。
佐野政言の刃が神聖視され、赤穂浪士の行動が義とされ、そして時代を経て日米の開戦が「やむを得なかった」と語られたように、物語の構造は塗り替られていく。
そしてその物語を欲したのは、いつも“私たち民衆”だった。
あの太平洋戦争。為政者だけでなく、民衆もまた熱狂することで加担し、後戻りできなくなった。
だからこそ今、私たちが知るべきなのは、語られてきた正義をそのまま信じることの危うさである。
静かな問い──森下佳子という語り手に寄せて
ドラマ『べらぼう』の中で田沼意知が登場する意味。
渡辺謙が田沼意次を演じる意義。
それはきっと、正義や改革といった表層的なテーマではなく、「語られすぎたものの危うさ」を語るための布石なのではないか。
今作では、佐野政言という人物が“時代に翻弄された弱き存在”として描かれている。
その姿は、民意に押し上げられ神とされた史実上の「佐野大明神」とは、まるで別人だ。
そこにこそ、森下佳子が描こうとしている“語られすぎた正義”と、その危うさが浮かび上がる。
森下佳子という脚本家は、派手さよりも“語られざる声”をすくいあげる書き手だ。
そしてこの作品の中に静かに佇む存在──蔦屋重三郎。
物語を作り、人々に届け、“見たい世界”を編んだ者。
この文章を通じて、私はひとつの問いに立ち戻る。
表現とは、誰のために、何のためにあるのか。
蔦屋とは何者だったのか。
寛政の改革という閉塞の時代に、森下佳子がこの“表現者”をどう描いていくのか──
その筆に、私は静かに注目している。