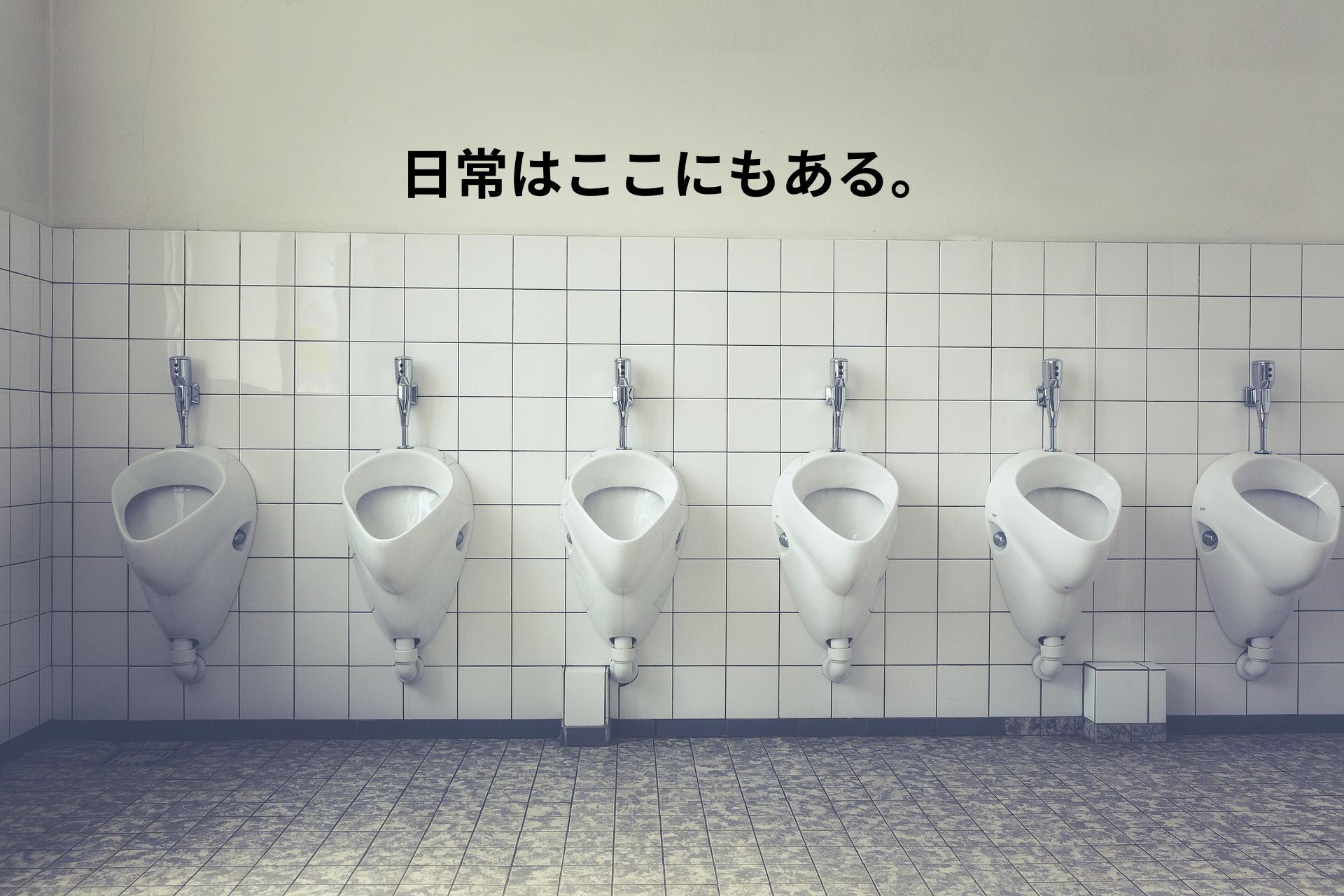頭で考える前に、静けさをひとつ
ふと、映画『日日是好日』が見たくなった。
静かにお茶をたてるだけの、あの淡々とした時間の流れ。
そこに、なにか大切なものが宿っている気がした。
もしかしたら、少し疲れていたのかもしれない。
言葉や情報の波に呑まれて、心の奥の感覚が乾いていたのかもしれない。
そんなとき、静かな茶室の空気に癒されるようにして、
この映画の世界に身をゆだねた。
そして、じわじわと沁み込んできたのは──
「感じる」ということの深さだった。
茶道が教えてくれた、“感じる”ということ
映画『日日是好日』は、茶道を通して感性を育んでいく女性たちの物語だ。
主人公・典子は、母に勧められて茶道を始める。
最初は戸惑いながらも、二十年以上の歳月のなかで、
ひとつひとつの所作に心を添えることを覚えていく。
武田先生の言葉が印象に残る。
「頭で考えないの。まず形から入りなさい。」
それは「考えるな、従え」ということではない。
むしろ逆だった。
茶室での作法は、感受性の器を整える準備。
身体を通して感じるための「静けさ」を育てていく。
たとえば、茶碗をまわす角度。
湯を注ぐ音。
お菓子をいただく間合い──
五感をひらいて、今この瞬間に触れる。
その繰り返しのなかで、少しずつ“わたしの感覚”が戻ってくる。
禅のまなざしで、世界を見つめ直す
茶道の根底には、禅の思想が流れている。
「不立文字(ふりゅうもんじ)」──言葉では語れない世界。
「只管打坐(しかんたざ)」──ただ坐ることに意味があるという教え。
判断する前に、まず“在る”という感覚に立ち返る。
それは、すぐに正解を求めようとする現代のわたしたちにとって、
ひとつの救いになるのかもしれない。
印象的な場面がある。
典子と従妹の美智子が、山あいの川辺を歩くシーン。
澄んだ水が流れ、夏の光が揺れている。
「見合いすることにしたの」と、静かに話す美智子。
その表情に、悩みの跡はなかった。
水音を背景に、彼女の言葉がまっすぐに流れていく。
それは、まるで方丈記の一節のようだ。
「行く河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。」
過ぎゆくものをとどめようとせず、
ただ静かに、今の流れを見つめる。
そんな時間のなかで、美智子は自分の人生にそっと向き合っていたのだろう。
なお、映画の原作となったエッセイは、森下典子さんの
『日日是好日―「お茶」が教えてくれた15のしあわせ』。
映画の静謐な世界を、言葉でも味わいたい方におすすめです。
この日、この気配、この一呼吸
あれこれ考えても、人生の正解はきっと誰にもわからない。
けれど、季節の移ろいに心を澄ませ、
お茶の湯気に目をこらし、
そっと吹き抜ける風に気づく──
そんな感覚がわたしの中に育っていくとしたら、
その一日は、もうすでに「好日」なのだと思う。
映画の終盤で、典子は静かにこう語る。
「頭でわかることと、感じることは、違うんだってこと。」
理屈ではなく、身体の奥にしみ込むように。
その言葉は、彼女自身が
長い時間をかけて「感じて」たどり着いた答えだったのだろう。
日々是好日──
今日という日が、晴れでも雨でも、喜びでも戸惑いでも、
そのままのかたちで愛おしくあるように。
今この瞬間を、静かに味わう。
その心が、わたしたちをすこし自由にしてくれる。