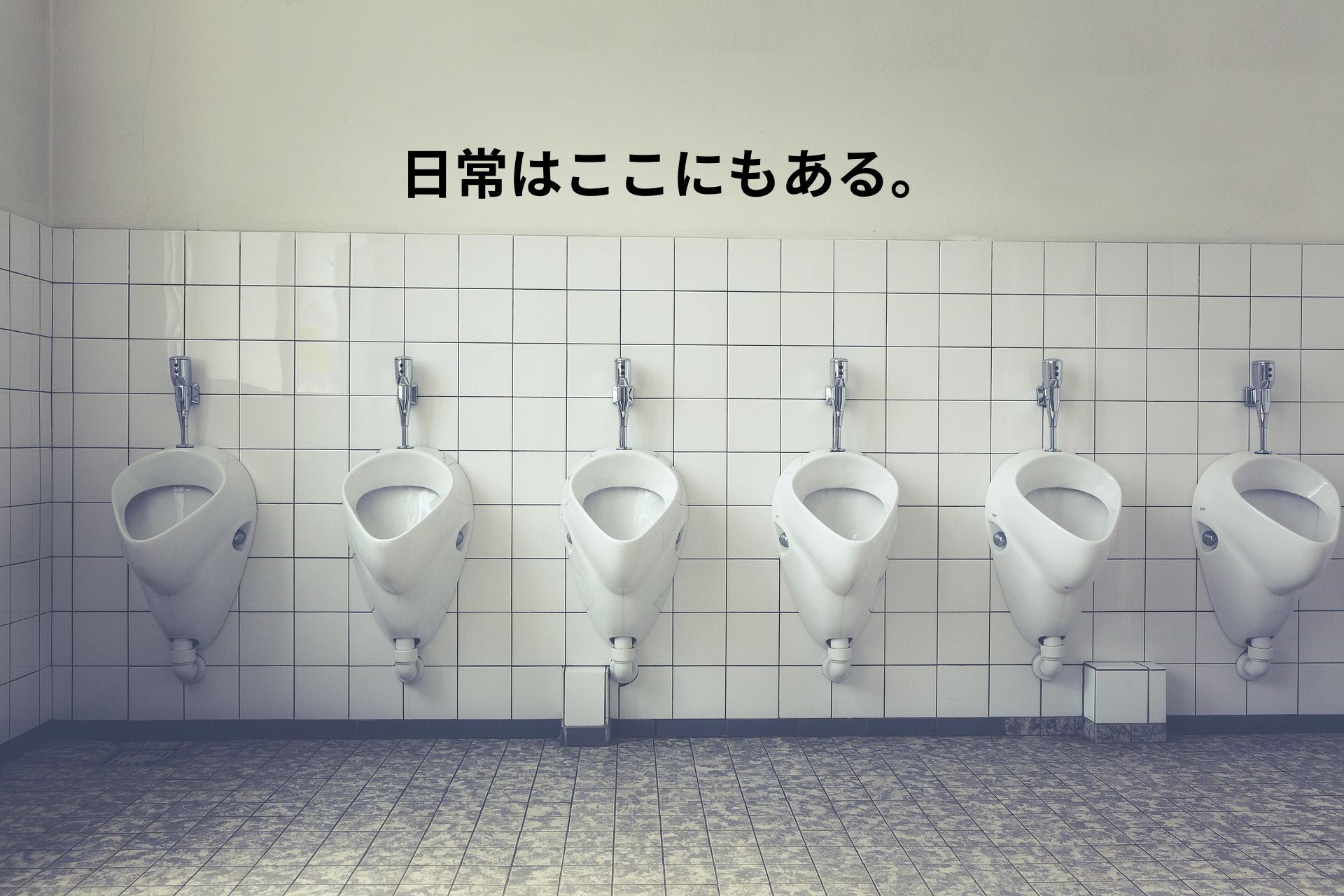ドラマ『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』の中で、
蔦屋重三郎が結婚したあとの喜多川歌麿の微妙な態度が、
心に静かに残っていた。
視線の揺らぎ、間合いの変化、少し遠くを見るような仕草。
言葉ではないところで伝わってくる、距離と寂しさ。
それは、まるで「自分の居場所がそっと変わっていった」と感じる、
あの時の痛み。
ふと頭に浮かんだのは、フィンセント・ファン・ゴッホと弟・テオのことだった。
そして私は気づいた。――あの表情の奥に、“芸術家の孤独”が静かに描かれているのだと。
理解者が変わるとき、世界もまた変わる
フィンセント・ファン・ゴッホにとって、弟テオはただの画商ではなかった。
絵がまったく売れなかった時期も、「君の描くものには価値がある」と言い続けた、唯一の理解者だった。
しかし、テオが結婚すると、ゴッホは目に見えない変化を感じ始める。
手紙の数が減り、言葉の温度が少しずつ変わる。
それは、「君が悪い」のではなく、「世界がもう、前と同じではなくなった」という感覚。
『べらぼう』の中で、歌麿が蔦屋の結婚後に見せたわずかな“揺れ”も、まさにそれに似ている。
かつては二人で世界を切り取っていたはずなのに、今はその構図に、もう自分はいない――。
猫のいる庭と、画家の居場所
ゴッホが晩年に描いた《ダウヴィニーの庭》には、二つのバージョンがある。
そのうち一枚には、画面の片隅に“猫”が描かれている。
整えられた庭。
咲き乱れる花。
人の気配が感じられる、生活の風景。
その隅に、ぽつんと佇む猫。
そこに描かれたのは、ゴッホ自身だったのかもしれない。
誰かの暮らしのなかに自分はもういない。
誰にも飼われず、誰にも必要とされず、それでもここにいる。
猫の眼差しには、そんな“存在の寂しさ”が静かに宿っているように思える。
そしてその作品の一つは、広島の美術館にも所蔵されている。
歌麿は、浮世絵で「心の奥」を描いた絵師
本来、浮世絵とは華やかで享楽的な世界を映す、江戸の“ポップカルチャー”だった。
多くの絵師が美人画を「理想美のカタログ」として描き、観る者を楽しませていた。
しかし、歌麿の描く女性たちは、どこかが違っていた。
視線が何かを追い、眉がわずかに揺れ、口元が言葉を飲み込む。
それは、「見せる顔」ではなく、「誰にも見せたくなかった瞬間の表情」だった。
彼は、型にはまった美女を描いたのではなく、
そこに生きていた“誰かの一瞬”を切り取った。
その表情に、観る者はふと自分自身の記憶を重ねる。
あの時、あんなふうに泣きたかった。
あの時、あんなふうに遠くを見ていた――。
浮世の表でなく、“裏”を描いた者たち
ゴッホも歌麿も、芸術という手段を使って、ただ美しさを描いたのではない。
心のなかの居場所を、筆で確かめていたのだ。
理解者がいて、だからこそ描けた。
けれどその理解者が別の世界を持ったとき、自分の居場所は、音もなく遠ざかっていく。
それでも描く。
誰に頼まれなくても、誰に評価されなくても。
描くことで、自分が“ここにいた”という痕跡を残すために。
スポンサーリンク
ゴッホの死に宿る、“最後の孤独”
ゴッホはその後、自ら命を絶った。
病の苦しみや、経済的な困窮。
けれどその根底に、「誰かとつながっていた糸が切れた」という感覚があったのではないか。
テオの結婚によって、弟の人生が穏やかに変化していったことは、祝福すべきことだったに違いない。
けれどゴッホにとっては、世界が“自分を必要としない形”に変わっていく過程だったのかもしれない。
『べらぼう』の中で、歌麿が蔦屋を見つめる眼差しにも、
そうした“失われゆく絆”への痛みがにじんでいた。
脚本家・森下佳子が描いた“共鳴する魂”
森下佳子さんの脚本には、しばしば「すれ違う心」と「孤独に堪える人間」が描かれる。
一緒にいたはずなのに、ある日ふと、違う風景を見ていることに気づいてしまう――
そんな静かな感情の揺れを、彼女は丁寧にすくいあげる。
『べらぼう』における歌麿と蔦重の関係。
それは、まるでゴッホとテオの魂の構図を、江戸に写したようでもある。
意識的か無意識かはわからない。
けれど、ここには確かに、時代を越えて響き合う“芸術家の孤独”が描かれている。
結び ― 孤独の中で、それでも描き続けた者たちへ
芸術とは、誰にも見せられなかった心を、
色や線に変えて、世界に残す行為なのかもしれない。
歌麿は、浮世絵という大衆的な形式のなかに、
そっと“心の奥”をにじませた。
ゴッホは、生活も名声も得られぬまま、
筆の先にだけ、居場所を持っていた。
描くことで、生きようとしたふたり。
その孤独な魂が、
時を越えて今も静かに、私たちの心に寄り添ってくる。