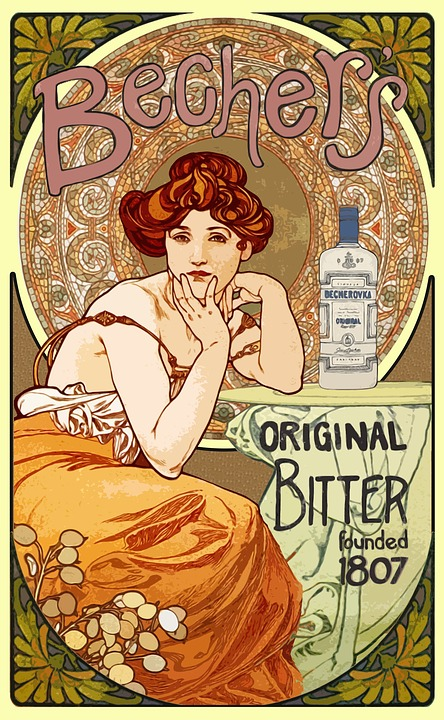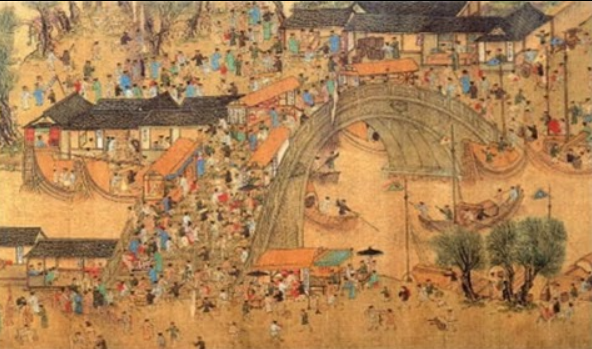速水御舟の革新的な「炎舞」
東京の山種美術館には速水御舟が31歳の時に描いた日本画の革新的な傑作「炎舞」があります。
御舟は何か月にも渡って炎の観察を続け、そして暗闇に立ち上るリアルな炎を描き上げました。
炎は昔学校で習ったコリオリの力で渦を巻き、炎の周りから新鮮な空気を吸い込み渦を巻いています。
物理的な理屈に沿った極めてリアルな姿を描き出しています。
炎を描くという極めてめずらしいその題材は、画期的な日本画として、同時代で最も早く重要文化財に指定されたことからもその評価の高さを示しています。
炎には何匹かの蛾が炎に魅せられるように吸い寄せられています。
御舟は炎舞を描く前に何匹もの蛾をデッサンしましたがそこに描かれた蛾は実際に存在する蛾ではありません。
御舟想像上の蛾なのです。
そのうちの一匹は炎の中に消えようとしています。
生から死へと旅立つ瞬間を表しています。
速水御舟という画家
速水御舟とはどのような画家だったのでしょうか。
明治17年に浅草に生まれ14歳の時画塾に入り基礎を学びました。
そして16歳には「小春」という作品を描き、技法を自由に使いこなし伝統絵画により正確に描写しています。
御舟は伝統的な海外にあきたらず、大正3年に若手画家と赤曜会を結成し、日本画に革新を目指しました。
そのトレードマークは「悪」。
古い日本画の伝統をこわし、新しい芸術をめざそうという心意気を表しています。
御舟という画家は、一旦画風を作り上げればそれをさらに壊し、その上にさらに新しい絵を生み出そうという勇気をもっていました。
その後、赤曜会は解散し、そして、出来上がったひとつの帰着が「洛北修学院村」という作品です。
群青色の草木の一本一本までが、細密に描き出された、極めて印象的なその作品は高く評価されました。
当時は大正デモクラシーの時代。
西洋の新しい技術が伝えられました。
殊に、白樺派が伝えたゴッホは、描き手の想いを強烈に伝え、当時の画家達に強烈な影響を与えました。
当時の洋画界では、岸田劉生が現れ、デューラーの影響を受けて、徹底した細密描写で娘の麗子像を描き、その中に真実を描きこもうとしていました。
当時、日本画は、伝統を重んじるばかりで御舟に革新の期待が集まりました。
写実の追及、そして写実を超えて
写実を追求して、「京の舞妓」という作品を描き上げます。
真実をつかむため、敢えてあさましく描こうと徹底した細密画は、酷しく批判されました。
大家、横山大観は激怒し、悪写実と酷しく批判したのです。
御舟自身、次第に写実一辺倒になっていくことに悩みました。
そこから、真実をつかみださなけれぼならないと悩みました。
写実を突き詰めた先でつかんだものが、「炎舞」という作品だったのです。
炎は螺旋を描いて舞い上がり、まるで生命のほとばしりのようです。
伝統的な日本画は輪郭線を描くことを基本としています。
日本画としては、新しい、輪郭線を描かない朦朧体という技法に横山大観は挑みますが、日本画ではないという批判を受けやめています。
御舟の炎舞は、まさに試行錯誤の結果、この朦朧体を完成させた作品になっています。
新しい表現を求め、西洋の絵のように、空気を捉えようと、伝統を打ち破り完成させた名作なのです。
スポンサーリンク